
昆虫標本の作り方
昆虫標本は、基本的には形を整えて乾燥すればよいだけで、決まった方法はありません。しかし、標本と呼べるには
正確なデータラベルが付いていること、同定(種を識別すること)に必要な足や触角が見やすくなっていることが、
最低条件です。飼育しているクワガタやカブトを殺して、標本にすることは抵抗がありますが、美しい標本を作るには
酢酸エチルなどで殺して標本にするのが好ましいようです。死んでしまうと、腐敗したり、カビが生えたりして
しまうからです。ここでは、飼育中に死んでしまったクワガタを標本にする方法を紹介します。
(私自身は、殺して標本にしたことはありません。でもお気に入りのクワガタやカブトを綺麗な形で残して、いろいろな
人に見てもらうのも一考かなと思います。実際、私のお気に入りのクワガタやカブトで、完品の標本はありません。)
①熱湯に入れる。
死んでしまったクワガタは、体が柔らかくても乾燥して固くなっていても、
とにかく熱湯のなかに入れます。そうすると、クワガタについているゴミや
害虫が取れます。約1時間もつけて置けば、柔らかくなります。この時、
体がバラバラになることがありますが、余程腐敗していない限り、
木工ボンドで修理できます(腐敗しているものは、標本にはなりません)。
②ティシュペーパーの上で水分を取り、ハケでゴミを落とす。
熱湯から出したクワガタをティシュの上に置き、水分を吸い取らせます。
このとき、ハケで細かいゴミもきれいに落とします。ゴミがついていると、
後からカビが生える原因になるのでしっかり落としましょう。きれいに
なったら、指で大アゴや足をある程度まで、整えます。指で足が動かな
ければ、もう一度熱湯の中に入れて作業を繰り返してください。
③胴体)を固定する。
展足板(ペフ板)の上に乗せて(発泡スチロール等でも可)、大アゴ・首
・胴体の3ヶ所を針で固定します。右肩部に直接昆虫針を刺して固定
しても良いと思います(ドイツ箱等に保管の場合)。大アゴの開きぐあ
いは、個人の自由ですが、左右対象 になるように固定しましょう。
(この位置に昆虫針を刺す(ドイツ箱等に保管する場合です)。)


④足を固定する。
前足・中足・後足をそれぞれ左右対称になるように針をクロスして
押さえるように刺し、固定します。


⑤足のツメを固定する。
すべての足のツメを下に向けて、開くように針で固定します。
この作業をするだけで、きれいな標本になります。
⑥触角(しょっかく)を整える。
触角を左右対称にして、大アゴと同じ高さに整えます。
全体のバランスを確認して全体のバランスが悪ければ、
整えます。ラベルも忘れずに標本の側に付けましょう。
(ブリードしたクワガタ・カブトは、学名・産地など、体長を
加えても良いかもしれません。天然物を採集した場合、
必ず日付け・採集者も記入しておいてください。)
⑦乾燥させる。
大きなダンボール箱などに、入れて乾燥させます。その中に乾燥剤(シリカゲル)と防虫剤(パラゾール)も入れて、
風通しの良い出来れば暗い場所で、約1ヶ月間、放置します。
⑧展足板から針を取り除く。
まず、1番壊れやすい触角の針から慎重に針を抜いていきます。
後は、展足した順番と反対の順番で針を抜いていきましょう。
⑨昆虫針を刺す(ドイツ箱等に保管の場合)。
右肩に昆虫針を刺します。オオクワガタなどは、とても上翅(じょうし)が固いので、針が曲がったり、
指を傷つけたりしないように注意しましょう。最後に、ラベルも昆虫針に刺します。


⑩小さめのケースなどで単体・ペアなどを保管する場合
私自身は、トランプケースのM(普通サイズ)とLを使用しています。最近では、100円ショップなどで
いろいろなケースがあるので試してみてください。下地が透明なケースの場合は、目立たないので
白いラベルなどを貼り付けます。標本の固定はケースにクッションになるような物を貼り付けて、
そのクッションに木工ボンド等で標本を固定すれば充分です。
(大型のカブトムシは、オリジナルの極厚プラボトルに保管してます。)

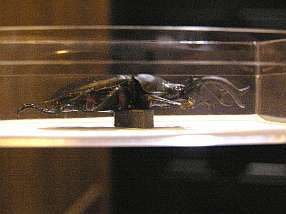
最後にラベルを貼って完成です。


ラップしておくと虫などの侵入を防いだり、汚さずに保管できます。
最後に。
私自身、生き虫を殺して標本を作ることは出来ません。
寿命や病死・事故死?した固体で完璧な標本を作るのも困難です。
人それぞれ考えは違うので方法は問いませんが、標本で残して見てもらう事は、大切なことなので
標本を作ったことのない方は、ぜひ挑戦してみてください。




